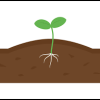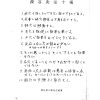陰陽について
陰陽は強くなったり弱くなったりして常に循環・均衡している。陰陽の動きを以下4つの種類で分類する。
相対(そうたい)相補(そうほ)消長(しょうちょう)転化(てんか)
1-1相対(そうたい)
自然界にあるものには、すべて相対する2つの面が存在していると考える。天と地、上と下、昼と夜のように、陰陽に分けることができる。
注 陰陽は、常に割合を変えながら変化を繰り返している。昼は陽で夜は陰であるが、真夜中から夜が明けるまでは陰の中の陽とあらわすように常に動いている。相対は二元論的概念である。
1-2相補(そうほ)
相補はお互いに共生しているため、どちらか一方のみでは存在することができない。陰がなければ陽は存在しないし、陽がなければ陰は存在しない。天がなければ地はなく、上がなければ下はない。
注 陰陽はお互いに別々に離れて存在することは出来ない。相補は一元論的概念である。
1-3消長(しょうちょう)
消長は、常に動いて、どちらかが盛んになると、もう一方は衰えることである。 季節の消長は、冬の陰が少しずつ夏の陽に変わっていくと陰は減り、陽は盛んになっていく。
注 春と秋は陰陽のバランスが安定しているため病気になりにくいという考えになる。
注 消長は量的位相概念である。
1-4転化(てんか)
陰は陽に転化し、陽は陰に転化することがある。固体から液体、液体から固体に変化するときに、固体は静、液体は動ととらえ、静としての陰と動としての陽が変化していることを意味している。
注 消長は量的であるが、転化は質的位相概念である。
2.治療における陰陽
2-1人体の陰陽分類(部位の陰陽)
自然を陰陽に分けたように人体も陰陽に分けることができる。それを整理すると次のようになる。
上半身 四肢 陽経脈 皮毛 血脈 背 腑 心 肺 胃 気
下半身 躯幹 陰経脈 肌肉 筋骨 腹 臓 腎 肝 脾 血津液
鍼灸治療では、すべての病気を陰陽の部位(経絡)における陰陽の気の変化(虚実、寒熱)としてとらえて治療する。人体のあらゆる部位や気血津液は陰陽のどちらかに属す。陰があればそれに対する陽があり、陽があればそれに対する陰がある。
注 相対的に分けるが陰陽ではなく、一気全体から見て、陽が多ければ陽となり、陰が多ければ陰となる。相対(そうたい)相補(そうほ)
2-2陰陽の働き(陰陽の生理)
経絡によって循環している陰陽の気がある。これら陰陽の気には次のような性質や働きがある。
2-2-1陰気の慟きと性質
陰気には堅める、縮める、引き降ろす、収斂する、藏する、生み出す、熱気を冷やす、鎮静するなどの働きがある。
注 性質や働きを陽とすれば、形質は陰である。
注 血は形質なので陰に属し冷やす作用がある。血には陽気もあって温める作用がある。陽の部位に血は陽に働き、陰の部位に血は陰に働く。相補(そうほ)消長(しょうちょう)
2-2-2陽気の慟きと性質
陽気には広がる、伸びる、上る、発散する、乾かす、熱する、寒気を除き沈滯しているものを賦活するなどの働きがある。
注 陽気は過剰になると逆に冷やすほうに働く。(陽極まりて陰を為す。)
素問陰陽応象大論「陽は殺す」「壮火の気は衰える」と表現している。
「殺す」や「衰える」は、陽が陰の方に働くことである。燃えてる火に酸素濃度の限界を超えると火の勢い強いほど早く消える。
相対(そうたい)相補(そうほ)転化(てんか)
2-3陰主陽従
鍼灸治療で「陰主陽従」の病理原則がある。陰の虚から病気が起こることで、陰の虚を主として証を表現している。臓や陰経を基盤にして、腑や陽経を働かせるという立場えある。そこに虚実が加わり、陰虚・陽虚・陽実・陰実となっている。
相対(そうたい)相補(そうほ)消長(しょうちょう)転化(てんか)
注 素問生気通天論「陰は精を蔵して亟を起こすものなり、陽は外をまもりて固めをなすなり」。
陰が内にあって陽の守りとは、陰が気血や津液を蔵して、その亟つまり働きを充分に発揮すれば、陽の部位に外邪の影響を受けることがない。
素問陰陽応象大論「陰は内にありて陽の守りなり、陽は外にありて陰の使いなり」
陰に気血や津液が充分にあれば、陽気の働きが活発になって適度に陽気を発散して、腠理の開闔を活発にする。だから陽は外にあって陰の使いであり、また外をまもる。
注 代謝に於いて、陰は同化的に働き、陽は異化的に働く。
2-4陰陽の交流と循環
①自然の陰陽 春夏秋冬のように陰陽には交流する性質がある。一日で言えば日が昇りかけて陽気が徐々に出てくる。日中になると陽気が盛んになり、日が西に傾くころになると陽気が少なくなって陰気が出てくる。そして夜になると陰気が旺盛になり、翌朝は陽気が出てくる。
②人体の陰陽 朝になると陽気が出て目が覚めて活動的になり、昼は適度に陽気を発散して腠理の開闔を活発にしている。夜になると陽気は内に引きこもり、逆に陰気が旺盛になって腠理を閉じ、外邪に影響されないように身をまもる。
③臓腑経絡の陰陽 脾胃で生成された陰陽の気血は、まず胸に昇り手の陰経を通って手の先に出る。そこから手の陽経に行き頭に昇って適度に発散する。次に頭から足に向かって陽経を通うて適度に陽気を発散しながら下降し、足の陰経を通って内に入る。このような循環をしながら昼間は外に陽気が多く内に少ない。夜は外に陰気が多く内には陽気が多くなっている。
相対(そうたい)相補(そうほ)消長(しょうちょう)転化(てんか)
注 陰陽五行説の由来
古代バビロニアの天文学を起源とし古代の中国に伝わる。
天体の太陽(日の別名)と太陰(月の別名)に由
来する二元(分)的関係の陰陽説と、水星・金星・火星・木星・土星という五つの惑星の数に対応して、五行思想が生まれている。
木は生命体で軟らかく陽気が増えて陰気が少なくなる状態の「少陰」
火は暑くて陽気が成熟した状態の「老陽」
土は陰と陽が中和された状態の「太極」
金は非生命体で硬く陰気が増えて陽気が少なくなる状態の「少陽」
水は冷たくて陰気が成熟した状態の「老陰」
古代バビロニア=メソポタミアの南部;現在のイラク;前2004-前
1530 年
注 伝統医学とは、
生命を「肉体、感覚、精神、魂の結合体」と捉え、健康とは「身体的、知的、社会的、倫理的、精神的に調和のとれた幸福である」と定義する。
注 健康の定義目標
伝統医学
体液のバランス・自然との調和、幸福感,至福、神人の一休化、宇宙的我の境地
現代医学
病気がないこと.肉休・精神・社会的健康 (WHO)
注 治療原理
伝統医学
同病異治・異病同治、養生を重視、好転反応、休質・休調に応じた個別治療、浄化・排泄療法、時間治療的概念
現代医学
同じ病気には,同じ治療(同病異治や異病同治はなO
生活習慣の是正を重視 単一成分による薬物療法。浄化・排泄より、投与・添加を重視
- 五行
3-1自然界も五行に分けられたが、人体の部位や働き、病気の原因、病理、病証なども五臓を中心にして五行に分類される。
| 肝・胆 | 魂 | 筋膜 | 目 | 怒 | 爪 | 酸 | 呼 |
| 心・小腸 | 神 | 血脈 | 舌 | 喜 | 面色 | 苦 | 笑 |
| 脾・胃 | 意智 | 肌肉 | 囗 | 思 | 唇 | 甘 | 歌 |
| 肺・大腸 | 魄 | 皮毛 | 鼻 | 憂 | 毛 | 辛 | 哭 |
| 腎・膀胱 | 精志 | 骨髄 | 耳 | 恐 | 髪 | 鹹 | 呻 |
3-2相生と相剋関係
①相生とは、相互助長、相互産生のことである。ある物事がほかの物事を促進したり、育てたりする関係である。
②相剋とは、相互抑制、相互制約のことである。ある物事が全体のバランスを保つために、制約したり抑制したりする関係である。(「剋」には「勝つ」という意味がある)
3-2-1相生関係
①肝は心を生む
脾胃で生成された血は肝に貯蔵されている。血は経脈によって心に送られ、それに宗気や栄気の働きが加わって心の活動が始まる。この関係が肝は心を生ずるである。
②心は脾を生む
心は常に活動している陽気の多い臓である。心の陽気を受けて脾が慟く。この関係が心は脾を生ずるである。
③脾は肺を生む
脾は胃腸に命令を出して気血津液を生成させている。生成した気血は肺気の循環によって全身に送られる。もちろん、肺そのものが必要とする気も脾胃で生成されている。この関係が脾は肺を生ずるである。
④肺は腎を生む
腎は津液の多い臟である。しかし、津液だけでは動けない。津液は気によって全身を循る。その気を送っているのが肺である。この関係が肺は腎を生ずるである。
⑤腎は肝を生む。
腎には津液が多い。この津液が肝の蔵している血を潤している。血にも津液が含まれていないと全身を循環することはできない。この関係が腎は肝を生ずるである。
3-2-2相剋関係
①肝は脾を剋す。
恒常性維持のためには、肝は血を脾から取り込ななければいけない。 肝は脾の血を必要としている。
②脾は腎を剋す。
恒常性維持のためには、脾は腎の津液から気血や津液を生成する必要がある。 脾は腎の津液を必要としている。
③腎は心を剋す。
恒常性維持のためには、心の陽気が腎の津液を循環させなければいけない。腎は陰気が津液とともに堅まっている。腎は心の陽気を必要としている。
④心は肺を剋す。
恒常性維持のためには、心が血脈を通じて、肺気で血を循環させなければいけない。心は肺の陽気を必要とする。
⑤肺は肝を剋す。
恒常性維持のためには、肺が肝の血を循環させなければいけない。肺は肝の血を必要としている。
注 生命の恒常性維持
注
| 木星 | 火星 | 土星 | 金星 | 水星 |
| 風 | 火 | 土 | 空気 | 水 |
| 風 | 熱 | 湿 | 燥 | 寒 |
| 成長 | 陽熱 | 生養 | 清粛 | 寒潤 |
| 青 | 赤 | 黄 | 白 | 黒 |
| 陰中の陽
少陰 |
陽中の陽
老陽 |
陰中の至陰
太極 |
陽中の陰
少陽 |
陰中の陰
老陰 |
五行には、惑星の運行と季節が関わっている。
4.気血津液
鍼灸治療は「気の医学」だといってよい。人体には気があって適度に循環、発散して健康を保っている。また気は血や津液を巡らせて身体各部を潤し養っている。その気に過不足(虚実)が発生すると病気になる。
生体のすべての働きを気の作用として解釈できる。それをさらに分けて気・血・津液・衛気・栄気・神気・宗気・精気等として分析する。
3-1先天の気
人は父母から受けた精をもって誕生する。これを先天の精。先天の精は腎にやどる。腎の精は神。つまり心の陽気を発生させる。この心の陽気が下焦に行って腎精と合したものを先天の気。これを命門の陽気ともいう。
先天の気は後天の気(飲食物の消化吸収によってできる気血津液)を生み出す原動力となる。生成された気血津液は、腎の津液や心の陽気となって先天の気を補充する。だから命門の陽気とは先天の気と後天の気が合したものである。
このように先天の気は後天の気を生み、後天の気は先天の気を補充する。先天の気が弱いと後天の気の生成も弱くなる。補充する気血津液も少ない。
4-2後天の気
水穀(飲食物)が脾、胃などの働きによって消化吸収されて後天の精となる。後天の精に、肺に取り入れられた天の気が合して気血津液が造られる。これを後天の気。後天の気には宗気、衛気、栄気、血、津液などがある。
①宗気
霊枢の邪客篇「五穀、胃に入るや、その糟粕、津液、宗気の分かれて三隧となる、故に宗気は胸中に積もり、喉唯に出で、以て心脈を貫きて呼吸を行う」
宗気は呼吸の原動力となる気で。また肺が血気を循環させる元となる気でも。肺が気を循環させると小便がよく出る。そのために宗気は膀胱に降って三焦の原気と合し、小便を出す働きもある。
②衛気(外を守る)
水穀によってできた糟粕が小腸から大腸に降りて行くあいだに、命門の陽気によって蒸し出される気を衛気。衛気は後天の気の一つで、常に循環している活動的な気、つまり陽気のことで。この衛気が胃に行けば胃の陽気となり、肺に行けば肺気となり、腎に行けば命鬥の陽気と呼び名が変わる。要するに全身を循環している。
衛気は昼間は皮膚や分肉の間を巡って陵理を開闔し、適度に陽気を発散して外界の気温などの変化から身体を守っている。もし外界からの刺激を受けると、そこに衛気が集まってきて輳理を閉じたり開いたりする。この時に衛気が虚していると腠理が開いたままになって汗が出やすくなったり、逆に閉じてしまって汗が出なくなったりする。汗が出ないと集まってきた衛気が停滞するので発熱する。
衛気は夜になると腎経から入って臓腑を巡る。心に行った衛気は血の陽気と合して君火(神)となる。君火は相火となって下焦に降りてきて、腎精と合して命門の陽気となる。また命門の陽気の働きからは三焦の原気と表現する。
③栄気と血(内を守る)
栄気も水穀が消化吸収されることによってできる。
霊枢の営衛生会篇「糟粕を泌し、津液を蒸し、その精微を化し、上りて肺脈に注ぐ、すなわち化して血となりて以て生身を奉く、これより貴きはなし、故に独り経隧を行くことを得る、名づけて栄気」
栄気と血は同じ。難經では栄血と表現し、栄血は経脈中を循環するのだから、経脈の虚実さえ調整すれば血も調整できると考えた。
しかし、治療から考えると、血を巡らす気を栄気だと考える。血を陰とし栄気を陽とする。なぜなら、血が関連する病証に熱性のものと寒性のものとがからである。
営衛生会篇「帝日く、それ血と気と名を異にして類を同じくするとは何の謂いぞや、岐伯答えて日く、栄衛は精気なり、血は神気なり、故に血と気と名を異にして類を同じくす」
分類は同じでも名前が違えは働きに違うからである。
注 「栄」は「榮」または「営」とも書くが、「栄」で統一している。
④津液
水が停滞している病気は多い。病的な水は津液の停滞から起こる。 津液から気血が造られるが、津液にも独自の働きがある。霊枢では津液の津は陽で液は陰である。
津液そのものは血にも含まれているので、血の作用と不可分で。血にも津液にも各所を潤す作用がある。陰陽に分けると陰の作用である。
4精気
精または精気といわれるものは、非常に範囲の広い使い方がされている。
広義には先天の気ができる元になるもの。
狭義には腎に藏されているもの。
五臓それぞれに蔵されているもの。
五臓の精気
①魂
魂は肝の蔵している精気で。肝の蔵している血と一体になっているので、
魂には積極的、・計画的な働きが。
②神
神には二つの意味が。狭義には心に蔵されている精気を神。これ
が虚すと死亡するのだが、その前段階としては精神が不安定な状態、いは痴呆、錯乱、意識不明の状態などが起こる。
広義の神は、霊枢の平人絶穀篇「五臓安定し、血脈和利すれば、精神すなわち居す。故に神は水穀の精気なり」と神で。脈でいえば胃気であり、皮膚でいえば光沢のことである。
そして、神は独立して存在するものではなく、形が健全であれば神が盛んであり、神が盛んならばまた形も補われる。形は陰に属し、神は陽に属す。
③意と智
意と智は脾の蔵している精気で。記憶力、思考力と関係する気である。
④魄
魄は肺の蔵している精気である。精神活動でいえば気力に関係する。
魄は宗気と同じものだといづてよい。胸に集まって呼吸や血を循環させる原
動力となる気で。これを胸の陽気。いは腫中の気といってもよい。
⑤精と志
精は腎の蔵している気で、生命力の根源意味から先に述べたように先
天の精ともいわれている。精気には陰気としての働きがから、精がしっか
りしていると腎の津液も多くなる。志は物事を継続的に実行させる気で精に含
まれている。
- 虚実
実とは ・病気の勢いや精神状態が高い状態まで進むこと(機能が亢進している状態) ・寒、暑、乾燥など体の外からはいってくる「邪気」が強い状態。
虚とは 体の栄養不足などが原因で体の機能が低下している状態 ・気・血が少ない状態。
治療における虚実
鍼灸治療では虚実に対して補瀉手技によって治療する。そのために病理はもちろん病証も虚実に鑑別できないと治療できない。ここでは虚実の
定義と種類について
広義には虚とは正気の虚のことであり、実とは邪気の実をさす。
寒熱病証を虚実に分けて行う補鴻と、病理の虚実に対して行う補瀉とは意味が違っている。病理の虚実に対する補瀉を本治法である。局所の病証の虚実に対する補滴は標治法である。
4-1精気の虚
鍼灸治療で臓腑経絡の虚をもって証を表現する。実際は精気の虚だけでは病気とはいえない。
ⅰ精気の虚は単なる疲労程度である。
ⅱこれに何らかの病因が加わると、精気の虚に各臓の持うてい’る気血や津液の虚も加わってくる。
ⅳここまで進むと病証が現われる。これが病理の虚である。
ⅴ病理の虚が発生すると、寒または熱の病証が現われる。
病因を内因、外因、不内外因と分けるが、どのような病因が加わるかによって病理、病証に違いが出てくる。
①精気の虚だけの時に外邪が加わって発病し、気血津液にまで変化が及ぶことがある。
②精気の虚に内因か不内外因が加わって、五臓の持っている気血津液までも虚させて発病することがある。
③この状態になった時に外因が加わって発病することもある。
上記の治療は虚している陰経をみつけて補法をし瀉法が必要かどうか区別する。同時に気血津液の不足も補われる。
注 病理の虚は気血津液の虚でもある。
肝は血を蔵する。
腎は津液を藏する。
肺は気を蔵する。
脾は気血津液を生成する。
注
病理の虚によって寒熱が発生し、臓腑経絡に波及して病証を現わすが、それらの部位にも治療を加えなければならない。その時に問題になるのが全体の鍼数や深さである。それを知るために、寒熱病証も虚実に区別する必要がある。
4-2病理の虚
陰の精気および、それぞれの蔵している気血津液が虚すから病気になる。そして各臓の虚によって違いがある。
①肝虚
肝の精気を魂。肝は血を蔵し、血は魂を蔵している。そのために肝の
精気の虚はイコール肝血の虚になる。だから肝虚である場合は血虚だと考えてよい。肝の気虚だけのはあり得ない。
肝の蔵している血が虚すと、その病理によって寒または熱の病証を現わす。肝虚寒証、肝虚熱証である。
②心虚
心虚はない。心は神精気を蔵している。また心は常に活動している陽
気の旺盛な臓である。このどちらが虚して死亡する。だから心虚証はないのである。
心が寒や熱を持って病証を現わしている場合は、他の臓の虚から発生した寒熱を受けたためである。
③脾虚
脾は意智の精気を持っている。同時に気血津液ともにある。脾虚には脾の気虚、脾の血虚、脾の津液虚などがある。これを病理で区別すると脾虚寒証か脾虚熱証のいずれかになる。
④肺虚
肺は魄の精気を蔵している。同時に肺は気を主る。だから肺の精気はイコール肺気と考えてよく、肺虚といえば気虚ことになる。
肺虚になるとやはり寒熱が発生する。その場合肺は表を主るから寒熱病証は陽経において発生する。
⑤腎虚
腎は精志の精気を蔵している。腎は津液を蔵している。精気と津液は一体である。腎の精気の虚は津液の虚をともなっている。病証には精気の虚が主な病証と津液の虚が主な病証とがある。命門の陽気の虚が主になっているもある。前者は腎虚熱証後者、腎虚寒証になる。
⑤腑の虚
腑は臓の支配を受けているので、各臓が虚になると表裏腑も虚になることがある。病理の虚によって発生した寒を受けるために脈も沈んで弱くなるか浮いて力がなくなる。
4-3実の定義と種類
一方に虚が発生すると一方に実が発生する。素問太陰陽明論「陽道は実し、陰道は虚す」ひとつの原則だが、実とは血や熱の停滞、充満した状態である。
臓の精気の虚に血や津液の虚が加わって病理の虚が起こると寒熱が発生する。寒または熱は他の臓腑経絡に波及する。このうち寒を受けた臓腑経絡は実にはならないが、熱を受けた部位は実になることがある。
注 脈診では熱を受けた部位の脈が強くなっているので診断できる。症状も同様に現わしている。
以下臓腑別に整理する。
①腑の実
ⅰ臓の津液が虚して発生した熱が腑に波及して実になる場合。たとえば脾虚胃虚熱証。
ⅱ臓の津液が虚して発生した熱が経絡に波及して実熱になる場合。脾虚陽明経実熱証。
ⅲ臓の津液が虚して発生した熱が他の腑に波及する場合。脾虚陰虚胆実証。
ⅳ臓の津液が虚して発生した熱が他の臓に波及あるいは他の臓が受けた熱が他の腑に波及している場合。脾虚肝実熱証で胆実。
②肝の実
肝実には三種類ある。
①脾虚肝実熱証 肝に熱が侵入して停滞した状態で、同時に脾の津液が虚している。
②脾虚肝実瘀血証 肝実熱はなくなったが、熱のために血が停滞して肝実瘀血になる。。体質として癆血が多い人も髀虚肝実瘀血になる。
③肺虚肝実証 肺気の循環が悪くなり、同時に腎の津液が虚したために潤いがなくなって肝に血が停滞する。
心の実
心実はない。しかし、心に熱が多くなるので心熱はある。心熱は腎虚、肝虚、脾虚などで発生した熱が波及して起こる。
④脾の実
脾は熱を受けつけないので実にはならない。ただし、他の部位で発生した熱を受けることはある。ところが脾が完全に熱を受けてしまうと死亡するので、通常は脾が熱を腑(主に胃)に返す。それでも太陰経が熱を受けて脾まで熱が波及していることはある。
⑤肺の実
肺は腑と同じく外気と接するところなので、腠理があって衛気が出入している。そのために熱が停滞充満することがある。外邪によって陽経
に発生した熱が内攻して起こる。あるいは、虚、肝虚、脾虚などで発生した熱が内攻して起こる。
⑥腎の実
腎は津液の多いところなので、熱が停滞して実になることはない。熱が多くなると津液が乾くだけである。
注 熱が多くなると津液が干からびて左尺中、腎部の脈が堅くなることがある。
注 病理による陰陽虚実分類
陰虚証 陰補陽瀉
肝虚熱証 脾虚胃虚熱証 腎虚熱証
陽虚証陰陽補
肝虚寒証 脾虚寒証 肺虚寒証腎虚寒証
陽実証陽瀉
脾虚陽明経実熱証 脾虚胃実熱証 肺虚陽実証
陰実証陰瀉
脾虚肝実
脾虚肝実熱証 脾虚肝実瘀血証 肺虚肝実熱証
4-4病証の虚実
①病理の虚実と病証の虚実
たとえば臓の陰が虚して熱が発生したとする。その熱は他の臓腑経絡に波及する。これが病理の虚実である。
もし頭部、背部、腹部などの経絡に波及して、その部の気血の循環を阻害すれば、そこに痛みなどの症状を現す。同時に圧痛、硬結、陥下などの局所病変を現わす。これを病証の虚実として区別する。
病証の虚実にも治療を加えなければならない。病証はもちろんのこと圧痛、硬結、陥下などの局所病変を虚実に区別して補湾しなければならない。
②虚実に区別する基準
虚実に区別する基準は症状と脈状と局所病変である。
ⅰ症状 大便や小便や汗が出ているの状態は虚のことが多く、逆にそれらが出ないのは実のことが多い。
ⅱ脈状 脈状が実であれば実のことが多く、虚であれば虚のことが多い。
ⅲ局所病変 按圧して痛みが増すようであれば実、気持ちよければ虚である。
注 急性感染症では症状と脈状を主にする。慢性疾患であれば触診の状態を優先して補瀉する。
ご覧いただきありがとうございます。 新潟県 長岡市 わかさ 鍼灸 整骨院 はり きゅう koukichi-wakasa.com