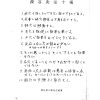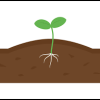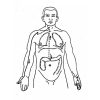五行論について
五行論とは、木・火・土・金・水の五つの行にょって、事物の生成変化や、組成・構造などを説明しようとするものである。もともとは事物を形づくる五つの材料から考えられていたた
やがて五行相互の間にある関係性が考えられ、よりカテゴリー的なものへ変わっていったとみられる。
五行論の内容は色体表を参照。
五行相互の関係性には、大別すると二種類あるが、いずれも循環を関係性のうちにとり込んでいる点は同じである。その一つは相剋説で、五行が相互に克服しあう関係をもとに循環関係を設定するものである。ふつうは木が土を克服して生じ、王が水をせきとめ、水は火を消し、火は金(金属)を溶かし、金は木を切り倒す、という形で、木→土→水→火→金という循環を考える。もう一つは相生説で、五行がたがいに他を生じあう形
で循環関係を考えてゆく。木から火が生じ、火から土(としての灰)が生じ、土から金が生じ、金は(溶けて液体としての)水を生じ、水は木を生じ育て、という形で、木→火→土→金→水という循環を考えるのが一般的である。
注 そのいずれの背後には四季と対応する循環の原理が、その基礎にある。
東西・南北の四方に春秋・夏冬の四季を配当し、中央の場をこれに加えた。そして木金・火水に土を加えた五行カテゴリーと結びつけられ、五行論は容易に循環性をとり込むことができた。季節とかかわるさまざまな自然(人事を含む)の諸事象を集めている。この季節に結びつけられることによって五行カテゴリーが飛躍的に豊かな内容をもつことになった。
注 季節を媒介として陰陽と五行のカテゴリーが結合した年代
は、紀元前三〇〇年頃と推定されている。五行論自体の成立は、それよりさらに遡ることになる。医学理論のうちに、いつ五行論がとり込まれたのかについては、不明な点が多い。春秋戦国期から末期(紀元前770-紀元前221)にいたる間には、五行の配当表が作成されるようになるから、それらが医学に影響を与えるのは自然のなりゆきである。前漢の文帝の時期(紀元前180 -前157)を境に、陰陽論から陰陽五行論へと医学理論が発展していったと説く仮説もある。
陰陽五行説 ’・< ゛’ ・’
流れの集合としての天地自然のうちに、それ自体が小さな流れの集合である人が生活する。天地自然の流れに沿い順うかたちで自己の生を律することが必要である。素朴な農事暦から出発した「時令」(季節ごとの。年中行事)は、人の生活を秩序づけ、時空の流れのリズムを説くものである。この自然の流れに陰陽五行説を指標とて説かれるようになる。
注 陰陽と四季とは、どちらも偶数だから相互の対応関係を作るのは容易だが、五行と四季との対応関係は作りにくい。
五行のうちの中央土が独立に四季のなかに場を占めることができないでいる。
土は季夏(夏の終わり)の位置を獲得し四季の各季節の終わりから土用にあてることで陰陽を四季の循環と結びつけるられた。
おだやかに生命を育てる春、繁茂させる夏、そして涼しさと収穫、冬じたくの秋、雪と風の冬という四季のめぐりと陰気と陽気の消長と、そして人が生き、あるいは死して葬られる大地に、人の世界の営みがら自然哲学が形成されていった。
ご覧いただきありがとうございます。 新潟県 長岡市 わかさ 鍼灸 整骨院 はり きゅう koukichi-wakasa.com