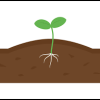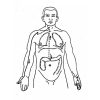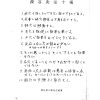九鍼十二原篇第一
九鍼十二原篇第一全文原文書き下し文現代語訳
本篇では、主に、古代にあったとされる九種類の鍼の名称・形状・用途と、刺鍼の際の疾・徐・迎・随・開・闔などの手法と、補瀉の効果について説明する。併せて、肘・膝・胸・臍などに分布する左右、正中を合わせて十二の原穴と、蔵府の疾病によってそれら十二の原穴を使い分ける治療方法について述べる。そこで、この篇を「九鍼十二原」と名づける。
【原文】
黄帝問於岐伯曰、余子万民、養百姓、而収其租税。余哀其不給、而属有疾病。余欲勿使被毒薬、無用砭石、欲以微鍼通其経脈、調其血気、営其逆順出入之会。令可伝於後世、必明為之法、令終而不滅、久而不絶。易用難忘、為之経紀、異其章、別其表裏、為之終始、令各有形。先立鍼経。願聞其情。
黄帝岐伯に問いて曰く、余万民を子しみ、百姓を養い、而して其の租税を収む。余其の給らずして、属ねて疾病あるを哀しむ。余毒薬を被らしむることなく、砭石を用いることなからしめんと欲し、微鍼を以て其の経脈を通じ、其の血気を調え、其の逆順出入の会を営なましめんと欲す。後世に伝うべく、必ずこれを為す法を明ら
かにせしめ、終わりて滅せず、久しくして絶えざらしめん。用い易く忘れ難く、これが経紀を為し、其の章を異にし、其の表裏を別ち、これが終始を為し、各おのをして形あらしめん。先に鍼経を立てん。願わくは其の情を聞かん。
【注釈】
子-愛する、慈しむという意味。
属-連続して、引き続きという意味。
毒薬を被る-「被」とは、受けるという意味。「毒薬」とは、治療に使う薬物の総称である。汪機の説「それで病を攻めることができるものは、みな毒という」。
砭石-古代、疾病を刺して治療するのに用いた尖った石。
経紀-筋道、順序という意味。
【現代語訳】
黄帝が岐伯に問う。「私は万民を慈しみ、百姓を養い、彼らから租税を徴収している。私は彼らの生活が自給出来るものでなく、さらには連続して疾病が発生しているのを哀れに思う。彼らの疾病の治療にあたって、私は薬物と砭石とを使うことなしに、微鍼を用いて経脈を通じさせ、気血を調和させ、経脈中の気血の往来、出入や会合を正常に回復させたいと考える。同時に、こうした治療方法を後世に残し、鍼治療の道理を明らかにし、それを永遠に滅びることなく、久しきにわたって伝わるようにさせたいと思う。容易に運用できてかつ忘れにくくさせるために、筋道をはっきりさせ、章節を区分し、表裏を弁別し、始めから終わりまで理論と実践とを一貫させ、併せて九鍼のそれぞれの形状をはっきりと記したいJそのために、まず『鍼経』を作らねばならぬ。私はこの問題について、あなたの意見を聞きたい」。
【訳注】
(一)この部分、「必明為之法令、終而不滅」と断句する説がある。楊上善が「法令とは、即ち針経の法なり。」と注釈したのに始まるものであるが、ここでは原訳(『霊柩訳釈』)によって句点を施し、「令」を使役として後の句に掛けて読んだ。
【原文】
岐伯答囗、臣請推而次之、令有綱紀、始於一、終於九焉。請言其
道。小鍼之要、易陳而難入。麤守形、上守神。禅乎、神客在門。未
覩其疾、悪知其原。刺之微、在速遅。麤守関、上守機。機之動、不
離其空。空中之機、清静而微。其来不可逢、其往不可追。知機之道
者、不可掛以髪。不知機道、叩之不発。知其往来、要与之期。麤之闇乎。妙哉、工独有之。往者為逆、来者為順、明知逆順、正行無間。逆而奪之、悪得無虚。追而済之、悪得無実。迎之随之、以意和之、鍼道畢矣。
岐伯答えて曰く、臣請うらくは推してこれを次し、綱紀あらしめ、一に始まり、九に終わらしめん。其の道を言わんことを請う。小鍼の要は、陳べ易くして入り難し。矗は形を守り、上は神を守る。神なるかな神、客門に在り。未だ其の疾を覩ざれば、悪くんぞ其の原を知らん。刺の微は、遅速に在り。麤は関を守り、上は機を守る。機の動は、其の空を離れず。空中の機、清静にして微なり。其の来たるや逢うべからず、其の往くや追うべからず。機の道を知る者は、掛くるに髪を以てすべからず。機の道を知らざれば、これを叩くも発せず。其の往来を知りて、これに与かるの期を要む。麤の闇なるかな。妙なるかな。工独りこれあり。往く者を逆と為し、来たる者を順と為し、明らかに逆順を知れば、正行して問うことなし。逆いてこれを奪わば、悪くんぞ虚なきを得ん。追いてこれを済わば、悪くんぞ実なきを得ん。これを迎え、これに随い、意を以てこれを和すれば、鍼道畢われり。
【注釈】
①小鍼-また「微鍼」とも称する。現代の毫鍼である。
②陳べ易く入り難し-「張介賓の説「陳べ易しとは、常法は言い易いということ。入り難しとは、精微で及びがたいということ」。
張介賓〉曰、易陳者、常法易言也、難入者、精微難及也、
③麤は形を守る-「麤」は、ここでは粗工を指す。技術の低劣な医家のことである。馬蒔の説「下工は形と跡のみに拘り、徒に刺法を守るだけである」。
④上は神を守る-「上」は、ここでは上工を指す。技術の高度な医家のことである。馬蒔の説「上工は人の神を守る。
およそ人の血気の虚実は、補うにも瀉すにも、ただ神を中心とする。この鍼の方法を用いるだけではないのである」。
⑤神なるかな、神客門に在り-「多紀元簡の説「小鍼解篇に、『神客とは、正邪が共にあること。神は、正気で、客は邪気である。門に在りとは、邪が正気の出入するところにしたがうことである』とある。この説によれば、神乎の二文字で句である。神客とは、神と客との意味である」。
⑥麤は関を守る-「技術の劣る医家は、ただ四肢の関節の周囲の経穴の治療のみを墨守する。「麤」は「麁」の異体字。
⑦上は機を守る-「「機」とは、気の動静を指す。「上は機を守る」とは、技術の高度な医家は、経気の往来の動静を待ち、補虚瀉実の剌法を施すことをいうのである。
〈張介賓〉曰、上守機、察氣至之動靜也、
⑧其の空を離れず-「空」は、孔のこと。経穴を指す。「其の空を離れず」とは、気の往来は、経穴を離れないということ。
⑨其の来たるや逢うべからず-「邪気がまさに盛んな時期には、迎えて補ってはいけないということ。張志聡の説
「その気がまさに来ようとするとき、邪気はまさに盛んである。邪気が盛んであれば、正気ははなはだ虚した状態になる。その気の来るのに乗じて、すぐに迎えて補ってはいけない、邪気の来るのを避けるべきである」。
⑩其の往くや追うべからず-「邪気が衰えて、正気がまだ回復していない時に、瀉法を用いてはいけないということ。張志聡の説「正気が行き、邪気がすでに衰えて、正気が回復しようとするときは、その気の行くのに乗じて、追って瀉法を施してはいけない。正気を害なう恐れがある。気の往来の機微をとらえるべきである」。
闇-「暗」の異体字。愚昧で明らかでないこと。
往く者を逆と為し、来る者を順と為す「往」とは、気の去ることをいい、「来」とは、気の至ることを言う。
張介賓の説「往は、気が去ることで、ゆえに逆という。来は、気が至ることで、ゆえに順という」。
〈張介賓〉曰、往、氣之去也、故爲之逆、來、氣之至也、故爲之順、
覩みる。じっと見る。
【現代語訳】
岐伯が答える。「それでは私の知っているところを、順を追って説明させてください。このようにしてこそ、条理が生まれ、一から九まで、終始の順序が乱れないのです。まず刺鍼による治療の一般的な道理についてお話しましよう。
小鍼による治療の要点は、話すことは比較的易しいのですが、技術が精微な境地にまで及ぼうとすると、かなり困難なのです。技術の未熟な医家は、ただかたちのみに拘って、変化を知りませんが、高度な技術を持つ医家は、病人の神気の盛衰に基づいて、補瀉の手法を使うことが出来ます。血気が経脈を循行していく過程で、その出入には一定の門戸があり、邪気がその門戸から人体に侵入しようとするのに、医家が詳しく病状を見ないで、どうして病変の発生する原因がわかるでしょうか。
鍼の技術の要は、刺鍼の部位が適当であることと徐疾の手法の正確な運用にあります。技術の未熟な医家は、四肢の関節付近の経穴を墨守して治療するだけですが、高度な技術を持つ医家は、経気の動静を観察し、虚実の変化を洞察するのです。経気の循行は、経穴を離れることはありません。邪気は経気の流動にしたがって動くものであり、経
穴に表れた経気の虚実の変化は清静微妙なもので、細心の注意が必要です。
邪気が盛んなときは、決して補法を用いてはなりません。邪を留めるのを防ぐためです。邪気がすでに去っていて、正気が衰えているときには、決して瀉法を用いてはなりません。正気を害なうのを防ぐためです。気の働きの虚実変化を理解すれば、補瀉の手法を正確に運用でき、毛筋ほどの間違いも起きるようなことがありません。気機の虚実の変化を理解しなければ、弦上の矢が、正確な時期をはずして放たれるようなもので、補瀉の手法を乱用すると、当然治療目的を達成することが出来ません。
ですから、気の往来の時期を理解してはじめて刺鍼の正確な時間を理解できるのです。未熟な医家はこのことになんとくらく無知なことでしょうか。また気の往来を知ることのなんと精妙な技術でありましょうか。高度な医家のみが
このことを把握できるのであります。気が去るとき経脈が空疎になるのを『逆』、気が来るとき経脈が充実するのを『順』といいます。逆順の理屈を解ってこそ、大胆に法に従って刺鍼することが出来るのです。経脈の循行方向に迎って瀉法を施すことができればどう
して実邪を泄することが出来ないようなことがありましょうか。経脈の循行方向に従って補法を施すことができれば、どうして正気を強化出来ないようなことがありましょうか。以上のように、迎随補瀉の方法を正確に把握し、さらに入念に観察するならば、刺鍼の主要な道理は、この中に尽くされているのであります」。
【訳注】
- 今は原訳に従い、「神乎、神客在門。」と読んでおく。小鍼解篇の断句がこの読み方を取る。もう一つ、『素問』八正神明論篇・『太素』本神論に「神乎神」という句が見えることを根拠に「神乎神、客在門。」と読む説もあり、句読上からはその方が無理がない。
〈張介賓〉曰、神乎神、言正氣盛衰、當辨於疑似也、客在門、言邪之往來、當識其出入也、設未覩其疾之所在、又惡知其當治之原哉、
【原文】
凡用鍼者、虚則実之、満則泄之、宛陳則除之、邪勝則虚之。大要日、徐而疾則実、疾而徐則虚。言実与虚、若有若無。察後与先、若存若亡。為虚与実、若得若失。虚実之要、九鍼最妙。補写之時、以鍼為之。写日、必持内之、放而出之、排陽得鍼、邪気得池。按而
引鍼、是謂内温、血不得散、気不得出也。補日、随之随之、意若妄
之。若行若按、如蚊虻止、如留如還。去如絃絶、令左属右、其気故
止、外門已閉、中気乃実、必無留血。急取誅之。
持鍼之道、堅者為宝。正指直刺、無鍼左右。神在秋毫、属意病者。審視血脈者、刺之無殆。方刺之時、必在懸陽、及与両衛。神属勿去、知病存亡。血脈者、在諭横居、視之独澄、切之独堅。
凡そ鍼を用うる者は、虚なれば則ちこれを実し、満っれば則ちこれを泄し、宛陳なれば則ちこれを除き、邪勝れば則ちこれを虚す。大要に曰く、徐にして疾なれば則ち実し、疾にして徐なれば則ちますと。実と虚とを
言わば、有るが若く無きが若し。後と先とを察れば、若しくは存ち若しくは亡う。虚と実とを為さば、得るが若く失うが若し。虚実の要は、九鍼最も妙なり。補写の時、鍼を以てこれを為す。写に曰く、必ず持してこれを内れ、放ちてこれを出だし、陽を排して鍼を得れば、邪気泄するを得。按じて鍼を引く、是を内温と謂う、血散ずるを得ず、気出づるを得ざるなり。補に曰く、これに随いこれに随う、意これを妄りにするが若し。若しくは行らし若しくは按じ、蚊虻の止まるが若く、留まるが若く還るが若し。去ること絃の絶ゆるが若く、左をして右に属がわしめ、其の気故に止まり、外門已に閉じ、中気乃ち実し、必ず留血なからん。急ぎ取りてこれを誅す。
鍼を持つ道は、堅なる者を宝と為す。正しく指して直刺し、鍼の左右するなかれ。神は秋毫に在り、意を病者に属す。審らかに血脈を視る者は、これを刺して殆うきことなし。刺すの時に方りて、必ず懸陽と両衛とに在
り。神属して去ることなければ、病の存亡を知る。血脈なる者は、愉の横居に在り、これを視れば独り澄み、これを切すれば独り堅し。
[注釈]
①宛陳なれば則ちこれを除く-「「宛陳なれば則ちこれを除く」とは、気が滞って口が経ったものは、これを排除すべきであるということである。
大要-古経の篇名である。
徐にして疾なれば則ち実-「鍼をゆっくり刺入し、素早く抜き去り、鍼を抜き出して急ぎ鍼孔を按ずる方法で、補法に属する。
④疾にして徐なれば則ち虚-鍼を素早く刺入し、ゆっくり抜き取り、鍼を抜き出して鍼孔を閉じない方法で、瀉法に属する。
⑤実と虚とを言わば、有るが若く無きが若し-「鍼下に気が有るものを「実」といい、鍼下に気が無いものを「虚」という。張介賓の説「実と虚とは、気の有無によるものである。気はもともとは形がないので、有るがごとく無きがごとしという。よくこれを見極めるものは、有無の間をすぐれて理解する」。
⑥後と先とを察す-「疾病の緩急を見極め、治療の前後の順序を決定すること。
⑦若しくは存ち若しくは亡む-「気の虚実に基づいて、鍼を留めるかどうかと、鍼を留める時間とを決定すること。「若」とは、或いはの意味。
⑧得るが若く失うが若し-「刺鍼の補瀉の作用を形容したもの。実証であれば、瀉して除くため、患者が失ったものがあるようになる。虚証であれば、補って実するため、患者が得たものがあるようになる。
⑨放ちてこれを出す-「鍼孔を大いに揺らして、邪気を排出させること。
⑩陽を排して鍼を得三種類の解釈がある。匸陽とは、皮膚の表層の部位を指す。
一、表層の部位を排して、邪気を鍼にしたがって外に排泄する。
二、陽とは、表陽を指す。表陽を排して、邪気を去るのである。
三、陽を排すを、押し上げると解釈する。孫鼎宜の説「排陽とは、推揚の意味で、鍼を捻ること。鍼を捻れば。邪は自ずとそれにつれ」。
⑥内温-「温」は、蘊に同じ。気血が内に蓄まること。
⑩意これを妄りにするが若し-「思い通りにしていて、心を配っていないかのようであること。
⑩若しくは行らし若しくは按ず-「「行」とは、鍼を行らし気を導くこと。「按」とは、経穴を按じて鍼を刺すこと。
⑩左をして右に属がわしむ-「右手で鍼を抜き、左手で急ぎ鍼孔を押さえること。
⑩堅なる者を宝と為す-「鍼を刺す時、鍼を持つに必ずかたく力を入れるべきことを言う。
⑩意を病者に属す-「患者に精神を集中させることを指す。
⑥懸陽-「張介賓の説「懸は、挙がるの意味。陽とは、神気なり。鍼を刺す時には、かならずまず神気を引き出す
ことを主とする。それで懸陽という」。
⑩両衛-張介賓の説「両衛とは、衛気は外にあり、皮膚の表面を守っており、脾気は陰にあって蔵府ぎ守っている。両者は神気が宿っており、そこなってはならない。鍼を用いるものは、初めにこれを気に留めておくべきである」。
⑩これを視れば独り澄む-「はっきり見えることを言う。
【現代語訳】
「おおよそ刺誡を用いた治療は、正気が虚していれば補法を用い、邪気が実していれば瀉法を用い、気血が鬱滞していれば、それを破り除く方法を用い、邪気が亢進していれば邪を攻める方法を用います。『大要』には、ゆっくり誡を刺人し素早く抜き去り、誡を抜いた後急いで誡孔を按ずるのが補法であり、誡を素早く刺人してゆっくり抜き出し、誡を抜いた後誡孔を按じないのが瀉法である、とあります。誡の下に気があるのが実であり、誡の下に気がないのが虚であり、気はもともとは形がなく、有と無との間にあるものです。病の緩急と気の虚実に基づいて補瀉の前後の順序を決め、気の運行に基づいて、誡を留める時間を決めるのです。もし刺法を把握すれば、補瀉虚実の目的に通じ、患者をして、補えば得たものがあるように感じさせ、瀉せば失ったものがあるように感じさせるものです。
虚実補瀉の要妙は、九誡が最も理想的であり、補瀉の効果は、刺誡の手法によって解決できます。瀉法を用いるときは、かならず誡を素早く刺入して気を得たのちゆっくり抜き去り、大いに誡孔を揺らして、表陽を開けば、邪気を外に洩らすことができます。もし瀉すべきところを誤って補い、先に経穴を按じて、ゆっくりと誡を刺入すると、血気が中にこもって外に発散せず、邪気が出て行かなくなります。補法を用いるときは、経脈の巡行方向にしたがって鍼を向け、ゆっくりと散漫な様子でそっと刺します。鍼をめぐらして気を導き、経穴を按して鍼を刺すとき、あたかも蚊が皮膚の上を刺しているようなあるかなきかの感覚があります。鍼を抜き去るのは速く、矢が弦から放たれたかのように、右手で鍼を抜き、急ぎ左手で鍼孔を按ずれば、経気は留まり、外に発散せず、中は充実し、留血の弊害もありません。もし皮下出血すれば、時を移さず除去しなければなりません。鍼を用いる法則は、堅く力を込めることが最も重要です。経穴にねらいを定めて、真っすぐに刺し、左右に偏ってはなりません。すこしのことも洞察して、病人の神の状態の変化に心を注ぎ、皮下の血脈に細心の注意をはらい、穴位
上の血脈を避けて鍼をします。このようであれば、よくない結果を生じるようなことがありましようか。鍼を始める時は、病人の神気を引き出し、患者の陰陽の両方の衛りをよく理解するようにします。注意力を分散させずにいて、やっと疾病の存在と、消失とを知ることが出来るのです。血脈が経穴の周囲に分布していることは、かなり容易に見て取れますし、手で按じさすってみると固い感触があります。」
【訳注】
(一)宛陳「宛」について原訳では、「音鬱」=「うつ」と読んでいる。
(こ「徐而疾則実、疾而徐則虚」部分は、解釈としては、『素問』『霊柩』中でも二通りあり、各おの、支持する学者が違う。原訳は張介賓の説に基づいており、ここではそれに従て読むこととした。
(三)「懸陽」「両衛」の解釈はそれぞれ問題となってきた。「懸陽」については、楊上善の説「鼻なり。鼻を明堂と為すなり」。張志聡の説「心なり」。劉衡如の説「目なり」などの解釈がある。原訳は張介賓の説に基づいている。
「両衛」は、現在では石原明氏の覆刻『太素』により「両衡」と作るのが一般的である。楊上善の説「五蔵六府の気色は明堂と眉上両衡の中に見ゆ。故に鍼を持つ者は、先に気色
を観、死生の候を知り、然る後に之を刺す。」ここでは原訳に従って両衛のままとする張介賓の説を取る。
【原文】
九鍼之名、各不同形。一日鐘鍼、長一寸六分。二目員鍼、長一寸六分。三日提鍼、長三寸半。四日鋒鍼、長一寸六分。五日鍍鍼、長四寸、広二分半。六日員利鍼、長一
寸六分。七日毫鍼、長三寸六分。八日長鍼、長七寸。九日大鍼、長
四寸。鐘鍼者、頭大末鋭、去写陽気。員鍼者、鍼如卵形。揩摩分間、
不得傷肌肉、以写分気。提鍼者、鋒如黍粟之鋭、主按脈勿陥。以致
其気。鋒鍼者、刃三隅、以発痼疾。
皷鍼者、末如剣鋒、以取大膿。員利鍼者、大如釐。且員且鋭、中身
微大、以取暴気。毫鍼者、尖如蚊虻喙、静以徐往、微以久留之涵養、以取痛痺。長鍼者、鋒利身薄、可以取遠痺。大鍼者、尖如梃、其鋒微員、以写機関之水也。九鍼畢矣。
九銭の名、各おの形を同じくせず。一に曰く、鑰銭、長さ一寸六分。二に曰く、員銭、長さ一寸六分。三に曰く、提銭、長さ三寸半。四に曰く、鋒賊、長さ一寸六分。五に曰く、皴銭、長さ四寸、広さ二分半。六に曰く、員利銭、長さ一寸六分。七に曰く、毫銭、長さ三寸六分。八に曰く、長銭、長さ七寸。九に曰く、大銭、
長さ四寸。鑰銭なる者は、頭は大にして末は鋭く、陽気を去り写す。員銭なる者は、銭は卵形の如し。分間を揩摩し、肌肉を傷るを得ず、以て分気を写す。提銭なる者は、鋒は黍粟の鋭の如く、脈を按ずるを主り、陥いらしむることなかれ。以て其の気を致す。鋒銭なる者は、刃三隅、以て痼疾を発す。皷銭なる者は、末は剣鋒の如
く、以て大膿を取る。員利鍼なる者は、大なること箴の如し。且つ員且つ鋭、中身は微かに大にして、以て暴気を耿る。毫鍼なる者は、尖は蚊虻の喙の如く、静にして以て徐ろに往き、微にして以て久しくこれを留めて養い、以て痛痒を取る。長鍼なる者は、鋒は利く身は薄くして、以て遠痒を取るべし。大鍼なる者は、尖は梃の如く、其の鋒は微員にして、以て機関の水を写すなり。九鍼畢われり。
【注釈】
①鏤鍼-『広雅』釈詁四の説「鏤、鋭なり」。鍼尖が鋭いことから、鏤鍼と名付けられた。
②鍍鍼-多紀元簡の説「提は、時(シ)と読むかまたは低(テイ)と読む。矢じりのこと」。鍼の形が矢じりに似ていることから名がついた。
鍍鍼-「皴」は、両刃の小刀。鍼の先が剣に似ていることからこの名がある。
驚ヤク牛の尾、または馬の尾のこと。
【現代語訳】
「九鍼の名はそれぞれ異なっており、その形状も各おの異なっています。第一の鍼は鏤鍼といい、長さ一寸六
分。第二は員鍼といい、長さ一寸六分。第三は提鍼といい、長さ三寸半。第四は鋒鍼といい、長さ一寸六分。第五は皴鍼といい、長さ四寸、広さ二分半。第六は員利鍼といい、長さ一寸六分。第七は毫鍼といい、長さ三寸六分。第八は長鍼といい、長さ七寸。第九は大鍼といい、長さ四寸。九鍼の効用も、その長さと形状の違いによって区別があります。鏤鍼は、鍼の頭が大きく末が鋭くて矢じりに似ており、浅刺に用いて、体表の邪熱を瀉すのに用います。員鍼は、鍼形が卵に似ていて、鍼先はまるく、用いて按摩して、分肉の間の疾病を治療しますが、肉を傷つけず、分肉の間の邪気を瀉すことができます。提鍼は、鍼先が、粟の粒のように微かに丸く、経脈を按摩し、気血を流通させます。ただし、深く肌肉を窪ませることがあってはなりません。でなければ、正気を害なってしまうのです。鋒鍼は、三面に鋭利な刃があり、頑固な病を治療するのに使います。皴鍼は、鍼先が剣鋒のようで、潰瘍を刺して、膿を出します。員利鍼は、形状は馬の尾のようで、鍼先は丸く鋭利で、鍼身はやや太く、急性の病に用います。毫鍼は、鍼先が蚊虻の喙のようで、静かに気を候って徐ろに刺入し、鍼身が細いので、置鍼して気を養うことができ、痛痒を治療するのに用います。長鍼は、鍼鋒は鋭利で、鍼身は薄く長く、日を経た
痒を治療します。大鍼は、鍼先は尖って鍼身はやや太く、杖のような形状をしており、先端は微かにまるく、関
節に溜まった水を瀉すのに用います。九鍼の形状と主治効果について、以上で論じ終えました」。
【原文】
夫気之在脈也、邪気在上、濁気在中、清気在下。故鍼陥脈則邪気
出、鍼中脈則濁気出、鍼大深則邪気反沈、病益。故旧、皮肉筋脈各
有所処、病各有所宜、各不同形、各以任其所宜。無実無虚、損不足而益有余。是謂甚病、病益甚。取
五脈者死、取三脈者倨、奪陰者死、奪陽者狂。鍼害畢矣。刺之而気不至、無問其数、刺之而気至、乃去之、勿復鍼。鍼各有所宜。各不同形、各任其所為。刺之要、気至而有効。効之信、若風之吹雲、明乎若見蒼天。刺之道畢矣。
夫れ気の脈に在るや、邪気は上に在り、濁気は中に在り、清気は下に在り。故に陥脈に鍼すれば則ち邪気出で、中脈に鍼すれば則ち濁気出で、鍼大だ深ければ則ち邪気反って沈み、病益す。故に曰く、皮肉筋脈に各おの処する所あり、病に各おの宜しき所あり。各おの形を同じくせず、各おの以て其の宜しき所に任ず。実することなく虚することなく、不足を損して有余を益す。是れ甚病と謂い、病益ます甚だし。五脈を取るものは死し、三脈を取るものは椢う。陰を奪うものは死し、陽を奪うものは狂う。鍼の害畢われり。
これを刺して気至らざれば、其の数を問うなかれ。これを刺して気至れば、乃ちこれを去り、復た鍼するなかれ。鍼に各おの宜しき所あり、各おの形を同じくせず、各おの其の為す所に任ず。刺の要は、気至りて効あり、
効の信は、風の雲を吹くが若く、明乎として蒼天を見る
が若し。刺の道畢われり。
【注釈】
①邪気は上に在り-「ここでは風熱陽邪が上部を侵すことを言う。
②濁気は中に在り「濁気」とは、飲食の滞った気。寒温か不適当だったり、飲食が不摂生だったりすると、濁気が腸胃にとどまる。そこで「濁気は中に在り」という。
③清気は下に在り-「「清気」とは、清冷寒湿の邪のこと。馬蒔の説「清湿の地気が人に中たるときには必ず足から入る。そこで清気は下に在りと言う」。
④陥脈に鍼すれば則ち邪気出づ-「張介賓の説「諸経脈の経穴は、多くくぼんだ中にある。そこで寒邪を除こうとすれば、各経脈のくぼんだところに刺さねばならない。そうすれば経気がめぐって邪気が出る。そこで陽邪の上にある者を取る、といったのである」。
⑤中脈に鍼すれば則ち濁気出づ-「「中脈」とは、中部陽明脈の合穴を指す。馬蒔の説「其の中脈に鍼すとは、足の陽明胃経の合に取るということで、即ち足三里穴を治療する」。足の三里穴を刺して、腸胃の濁気を排出するのである。
鍼大だ深ければ則ち邪気反って沈む-「浅く刺すべき病に、深く刺すと、かえって邪を深く引き込んでしまう。
五脈-五蔵の経穴。
三脈を取るものは框-「「三脈」とは、手足の三陽脈である。
「訌」は、衰弱するという意味。手足の三陽の経穴を瀉すと、形気が衰弱する。
【現代語訳】
「およそ邪気が経脈を侵して発病するとき、風熱の邪は多く人体の上部を害ない、食物の停滞は人体の中部に留まり、清冷寒湿の邪気は多く人体の下部を害ないます。よって、刺鍼の部位もおのおの異なります。上部の各経脈の諭穴を刺せば風熱の邪を外に出し、陽明の合穴を刺せば胃腸の内部の積滞を除くことができます。病気が浅い部分にあれば深く刺してはいけません。邪気を引き込むことになり、病を重くしてしまいます。それゆえ次のように言うのです。皮肉筋脈にはおのおの異なる部位があり、鍼を刺す深さも、病気によってそれぞれ適うところがあるのです。九鍼の形状はそれぞれ違っており、病状によって適当なものを選んで用い、実証には補っ
てはならず、虚証には瀉してはなりません。そのようにすると、不足を損ない有余を益して、病気を重くしてしまいます。精気が虚している病人に、誤って五蔵の経穴を瀉してしまうと、必ず陰虚になり死んでしまいます。
陽気が不足している病人に、誤って三陽経の経穴を瀉してしまうと、必ず正気が衰弱して錯乱してしまいます。
以上のことから、誤って陰経を瀉すと蔵気を消耗して死亡し、誤って陽経を瀉すと陽気を消耗して発狂してしまいます。刺鍼の誤用の弊害は、大体このようなものです。
鍼を刺すときは経気の到来を候わなくてはなりません。気が至らないようならば至るまで待っていることが必
要で、施術の回数に拘らなくてもよいです。鍼の下に気を得たら、すぐに鍼を抜くべきで、治療を継続してはな
りません。九鍼はおのおの適応証が異なっており、その形状も一つではないので、病状によって選び用いてはし
めて、必要に適うようになります。これは刺鍼の重要なポイントです。鍼をした時は、気を得て初めて効果が現
れるのですが、その顕著なものは、まるで風が雲を吹き払い、暗天から晴天へと一転したようなものです。これで、鍼治療の道理は説明し終えたことになります」。
【原文】
黄帝目、願聞五蔵六府所出之処。岐伯囗、五蔵五倫、五五二十五倫、
六府六倫、六六三十六倫。経脈十二、絡脈十五、凡二十七気、以上
下。所出為井、所溜為榮、所注為倫、所行為経、所入為合、二十七
気所行、皆在五倫也。節之交、三百六十五会。知其要者、二言而終、
不知其要、流散無窮。所言節者、神気之所遊行出入也、非皮肉筋骨也。
黄帝曰く、願わくは五蔵六府の出づる所の処を聞かん。岐伯曰く、五蔵五倫、五五二十五倫、六府六倫、六六三十六諭。経膕十二、絡
脈十五、凡そ二十七気、以て上下す。出づる所を井と為し、溜るる所を榮と為し、注ぐ所を倫と為し、行る所を経と為し、入る所を合と為す。
二十七気の行る所、皆五倫に在るなり。節の交、三百六十五会。其の要を知る者は、二言にして終わる。其の要を知らざれば、流れ散じて窮まりなし。言う所の節なる者は、神気の遊行出入する所にして、皮肉筋骨に非ざるなり
【注釈】
五蔵六府の出づる所の処-蔵府がそれぞれに接続している経脈の脈気が出るところである。
二十五箇-馬蒔の説「五蔵は、心・肝・脾・肺・腎である。蔵ごとに井・榮・箇・経・合の五箇穴があるので、五五二十五愉である」。
③六六三十六脯-馬蒔の説「六府は、胆・胃・大腸・小腸・三焦・膀胱である。府ごとに井・榮・諭・原・経・
合の六諭穴があり、六六三十六臓となる」。
絡脈十五-十二経脈に各おの一つ絡脈があり、任脈・督脈・脾の大絡を加えて十五絡脈である。
出づる所を井と為す-「楊上善の説「井は、古くは泉の湧き出るところを井と呼んだ。・:(中略)人の血気は、四肢に湧き出るので、脈の出る所を井という」。
⑥溜るる所を榮と為す-「「榮」は『説文解字』水部に、「ごく細い水」とある。「溜るる所を榮と為す」とは、腥
気が通り過ぎる所を形容しており、泉から流れだした水が細い流れを作っていることを表す。
⑦注ぐ所を肺と為す-「腥気がここまで流れてきてまた別の所へ運ばれてゆくことを形容したものである。張介賓
の説「注は、注ぐという意味である。諭とは、運ぶという意味である。腥がここに注ぎ込んでまた別の所へ運ばれ、気は徐々に盛んになって行く」。なお、『甲乙経』では、この下に「過ぐる所を原と為す」とある。
行る所を経と為す-「経腥がここを通過することを形容する。楊上善の説「経とは、通るということである」。
入る所を合と為す-「脈気が集合するところを示す。張介賓の説「腥気がここに至ると、しだいに深くなり、内
に入って合流する」。
⑩節の交匸二百六十五会-「節の交」とは、人体の関節どうしが出会っている間隙のことである。これらの間隙は三百六十五あって、経脈中の気血がおのおの部分を潤している結節点である。
【現代語訳】
黄帝がいう。「五蔵六府の脈気が出てくる状況を理解したい」。
岐伯がいう。「五蔵の経脈には、それぞれ井・榮・輸・経・合の五つの諭穴があり、合計五五二十五の諭穴が
あることになります。六府の経脈には、井・榮・輸・原・経・合の六つの愉穴があり、合計六六三十六の諭穴があることになります。人体には十二の経脈、十五の絡脈があり、経絡の気はみなで二十七、全身を上下に運行しています。脈気の出てくるところを井穴と呼び、腥気の流れて行くところを榮穴と呼び、脈気の注ぎ運ばれて行
くところを輸穴と呼び、腥気の通過するところを経穴と呼び、脈気が集まるところを合穴と呼びます。これら二
十七の気の運行はみなこの五輸穴の中にあります。人体の関節などの出会う間隙は、合わせて三百六十五ありま
す。これらの要点を理解すれば、煎じつめれば匸言ですみますが、この要点を理解しないと、散漫になってまとまりかっかず、これらの諭穴について容易に理解が出来ないものです。ここでいう節とは、脈気の流行出入する場所であって、皮肉筋骨といった局部のことではないのです」。
【訳注】
(匸「榮」は、史椹の音釈に従えば、「音営」-「えい」と読むことになり、原訳でもそれに傲って音注をつけている。
【原文】
覩其色、察其目、知其散復。一其形、聴其動静、知其邪正。右主
推之、左持而御之、気至而去之。
其の色を覩、其の目を察、其の散復を知る。其の形を
一にし、其の動静を聴き、其の邪正を知る。右はこれを推すを主り、左は持してこれを御し、気至れば而ちこれを去る。。
【注釈】
①右はこれを推すを主る-「-「右手で鍼を刺入することを言う。張介賓の説「右手は推すを主るとは、鍼を刺入するからである」。
②左は持してこれを御す-「左手で鍼を保持することを言う。張介賓の説「左は持してこれを御すとは、護持するからである」。
③気至れば而ちこれを去る-「気を得たのち鍼を抜き去ることを言う。張介賓の説「邪気が去って穀気が至れば、鍼を抜く」。
【現代語訳】
「患者の顔面の色と目の状態とを観察し、神気の有無、去来の様子を知ることができ、病人の形態・動静・声の変化から、邪正と虚実とを診断できます。然るのち、右手で鍼を刺入し、左手で鍼を保持して、気の至るのを待ち、気が至れば鍼を抜き去るのです」。
【原文】
凡将用鍼、必先診脈、視気之劇易、乃可以治也。五蔵之気已絶於
内、而用鍼者反実其外、是謂重竭。重竭必死、其死也静。治之者輙反其気、取腋与膺。五蔵之気已絶於外、而用鍼者反実其内、是謂逆厥。逆厥則必死、其死也躁。治之者反取四末。刺之害。中而不去、則精池、害中而去、則致気。精泄則病益甚而権、致気則生為癰瘍。
凡そ将に鍼を用いんとすれば、必ず先に脈を診、気の劇易を視て、乃ち以て治すべきなり。五蔵の気已に内に絶え、而るに鍼を用いる者反って其の外を実するは、是れを重竭と謂う。重竭なれば必ず死し、其の死するや静なり。これを治する者輙ち其の気に反して、腋と膺とに取ればなり。五蔵の気已に外に絶え、而るに鍼を用い
る者反って其の内を実するは、是れを逆厥と謂う。逆厥なれば則ち必ず死し、其の死するや躁なり。これを治する者反って四末に取ればなり。刺の害、中たりて去らざれば、則ち精泄し、中たらずして去れば、則ち気を致す。
精泄すれば則ち病益ます甚だしくして框え、気を致せ
ば則ち生じて癰瘍を為す。
【現代語訳】
「およそ鍼を用いる前には、必ずまず脈状を診察し、蔵気の病状の軽重を理解してから治療法を決定します。
五蔵の気がすでに内で絶えている状態、これを陰虚証といいますが、鍼を用いて其の外側にある陽経を補ってしまうと、陽はますます盛んになって陰はますます衰え、五蔵の精気がさらに虚してしまいます。これを重竭と呼
びます。重竭になると必ず死にますが、死ぬときは静かです。これは医家が陰陽の経気と補瀉の原則に反して、腋や胸の経穴を取ったからなのです。五蔵の病変により、正気が外に虚してしまったものを陽虚証といいますが、鍼を用いて内側にある陰経を補ってしまうと、陰はますます盛んになって陽気は内に衰え、四肢の冷えと萎えを引き起こします。これを逆厥と呼びます。逆厥もまた必ず死亡しますが、死ぬときは騒いで安定しないものです。
これは医家が誤って四肢の末端の経穴を取って、陽気を尽きさせてしまったためにもたらされたものなのです。
およそ鍼を刺すには鍼を留めておく時間を把握していなければなりません。刺鍼してすでに病の急所に中ったと
き、鍼を留めて抜かずにおくと、きっと精気を外に漏らしてしまいます。もし鍼が病の急所に当たらないうちに鍼を出してしまうと、邪気を留まって散じなくさせてしまいます。精気が漏れると疾病を重くさせ身体を衰弱させます。邪気が去らずに肌膚に停滞すると癰瘍を生じます」。
【訳注】
(一)寒熱病篇及び『太素』巻二十一九鍼要道は「害」を「不」に作る。原訳書も「不中而去」に従って訳している。
【原文】
五蔵有六府。六府有十二原。十二原出於四関、四関主治五蔵、五
蔵有疾、当取之十二原。十二原者、五蔵之所以真三百六十五節気味也。五蔵有疾也、応出十二原、而原各
有所出、明知其原、覩其応、而知五蔵之害矣。
五蔵に六府あり。六府に十二原あり。十二原は四関に出で、四関は五蔵を主治す。五蔵に疾あれば、当にこれを十二原に取るべし。十二原なる者は、五蔵の三百六十五節に気味を禀くるゆえんなり。五蔵に疾あるや、応は十二原に出で、而して原に各おの出づる所あり、明らかに其の原を知り、其の応を覩れば、而ち五蔵の害を知る。
【注釈】
①四関-「両肘、両膝の四つの関節のこと。
②気味-孫鼎宜の説「気は、之と作るべきであって、ここでは草書を読み誤ったのであろう。味は、会と作るべきであって、音が似ているので誤ったのであろう」。
【現代語訳】
「五蔵六府の気は、表裏で通じあい、蔵府経絡は、内外で応じあっているものです。そこで十二原穴があり、十二原の経気は四肢の関節に出ており、四関の原穴は五蔵の疾病を主治します。ですから、五蔵に病があれば、十二原を取るべきです。十二原は、五蔵が水穀の気味を受け、その精気が三百六十五節に注ぎ、皮膚肌肉を潤し、全身を養うものです。五蔵に病がある時は、反応は十二原穴に現れるため、はっきりと原穴の性質を理解し、十二原穴の反応を観察すれば、五蔵の病変を知ることが出来るのであります」。
[訳注]
(一)『霊柩』諸本では「二」と作る。『太素』巻二十一諸原所生・『甲乙経』巻一十二原第六では「而」に作る。日抄
本では「十二」に作る。『霊柩』諸本のままでは意味が通じないため、原訳と『太素』『甲乙経』に従い、「而」と改めて読むこととした。
【原文】
陽中之少陰、肺也。其原出於太淵。太淵二。陽中之太陽、心也。其原出於大陵。大陵二。陰中之少陽、肝也。其原出於太衝。太衝二。
陰中之至陰、脾也。其原出於太白。太白二。陰中之太陰、腎也。其原出於太鈴、太鈴二。膏之原、出於鳩尾。鳩尾一。肓之原、出於胖腴。胖腴一。凡此十二原者、主治五蔵六府之有疾者也。脹取三陽、喰泄取三陰。
陽中の少陰、肺なり。其の原は太淵に出づ。太淵二。
陽中の太陽、心なり。其の原は大陵に出づ。大陵二。陰
中の少陽、肝なり。其の原は太衝に出づ。太衝二。陰中
の至陰、脾なり。其の原は太白に出づ。太白二。陰中の
太陰、腎なり。其の原は太鄭に出づ。太鈴二。膏の原、
鳩尾に出づ。鳩尾一。肓の原、胖腴に出づ。胖腴一。凡
そ此の十二原なる者は、五蔵六府の疾あるを主治する者なり。脹は三陽に取り、喰泄は三陰に取る。
【注釈】
①胖腴―任脈上の気海穴を指す。
【現代語訳】
「肺は陽中の少陰に属し、その原穴は太淵穴です。太淵穴は左右合わせて二穴。心は陽中の太陽に属し、其の原穴は大陵穴です。大陵穴は左右合わせて二穴。肝は陰中の少陽に属し、その原穴は太衝穴です。太衝穴は左右合わせて二穴。脾は陰中の至陰に属し、その原穴は太白穴です。太白穴は左右合わせて二穴。腎は陰中の太陰に
属し、その原穴は太鈴穴です。太鈴穴は左右合わせて二穴。膏の原穴は、任脈中の鳩尾です。鳩尾は一穴。肓の
原穴は、臍下の気海穴です。気海穴は一穴。以上、五藏の原穴はおのおの二穴ずつで、膏と盲の両方の原穴を加えて、合計十二穴。これらで蔵府表裏の気を通しさせ、五蔵六府の病を治すことができるのです。およそ腹脹の病には足の三陽経の経穴を、下痢には足の三陰経の経穴を耿って治療します」。
【原文】
今夫五蔵之有疾也、譬猶刺也、猶汚也、猶結也、猶閉也。刺雖久、
猶可抜也。汚雖久、猶可雪也。結雖久、猶可解也。閉雖久、猶可決
也。或言久疾之不可取者、非其説也。夫善用鍼者、取其疾也、猶抜
刺也、猶雪汚也、猶解結也、猶決
閉也。疾雖久、猶可畢也。言不可治者、未得其術也。
今夫れ五蔵の疾あるや、譬うれば猶お刺のごときなり、猶お汚れのごときなり、猶お結ぼれのごときなり、猶お閉ずるがごときなり。刺すこと久しと雖も、猶お抜くべきなり。汚るること久しと雖も、猶お雪ぐべきなり。結ぼるること久しと雖も、猶お解くべきなり。閉ずること久しと雖も、猶お決するべきなり。或るひと久疾
の取るべからざる者を言うは、其の説に非ざるなり。
夫れ善く鍼を用いる者は、其の疾を取るや、猶お刺を抜
くがごときなり、猶お汚れを雪ぐがごときなり、猶お結
ぼれを解くがごときなり、猶お閉ずるを決するがごとき
なり。疾久しと雖も、猶お畢わるべきなり。治するべか
らずと言う者は、未だ其の術を得ざるなり。
【注釈】
①雪ぐ-「洗浄する、拭い去るという意味。
【現代語訳】
「ここで五蔵に疾病があった場合の状況を説明しましよう。五蔵に疾病があるとは、体にとげが刺さったような、物体に汚れが付いたような、縄に結び目が出来たような、河川が土砂でつまるようなものなのです。とげが刺さって久しいとは言っても、抜くことはできます。汚れが付いて久しいとは言っても、洗い落とすことはできます。結び目ができて久しいとは言っても、解くことはできます。河川が土砂でつまって久しいとは言っても、流れるようにすることはできます。病気が長くなると、治せないという人がいるが、これは正しくありません。鍼の用い方に精通した医家が、疾病を治すのは、とげを抜くようなものであり、汚れをすすぐようなものであり、
縄の結び目を解くようなものであり、閉塞を通じさせるようなものであります。病気になっている時間が長くても、やはり治すことはできます。治せないなどという医家は、ほんとうはまだ刺鍼の技術を把握していないのです。」
【原文】
刺諸熱者、如以手探湯、刺寒清者、如人不欲行。陰有陽疾者、取
之下陵三里、正往無殆、気下乃止、不下復始也。疾高而内者、取之陰之陵泉、疾高而外者、取之陽之陵泉也。
諸熱を刺す者は、手を以て湯を探るが如くし、寒清を刺す者は、人の行くを欲せざるが如くす。陰に陽疾ある者は、これを下陵三里に取り、正しく往きて殆うきことなく、気下れば乃ち止め、下らざれば復た始むるなり。
疾高くして内なる者は、これを陰の陵泉に取り、疾高くして外なる者は、これを陽の陵泉に耿るなり。
【注釈】
①手を以て湯を探るが如い-毫鍼で諸熱病を治療する時は、軽く浅くすべきで、手で湯を探るかのように、一触即発であることを言う。張介賓の説「手を以て湯を探るがごとしとは、軽やかにしなければならない。熱は陽に属し、陽は外を主るから、治法はそのようにすべきなのである」。
②人の行くを欲せざるかごとし-「鍼を留めるの意味。張介賓の説「人の行くを欲せざるかごとしとは、去りがたいという意味である。陰寒が凝滞すれば、気を得ることは難しいので、鍼を留めるべきなのである」。
③陰に陽疾ある者-熱が陰分にあることを指す。
④下陵三里-足の三里穴のこと。本輸篇では、「下陵穴は膝下三寸にある」という。
⑤疾高くして内なる者-病気の位置が上で、蔵に属すものを指す。張介賓の説「疾高き者とは、上にあるものであり、下して取るべきである。そこで高くて内にある者は、蔵に属しているので、足の太陰の陰陵泉を取るべきである。」
⑥疾高くして外なる者-病気の位置が上で、府に属すものを指す。張介賓の説「高くて外にあるものは、府に属している。そこで足の少陽の陽陵泉を取るべきである」。
【現代語訳一
「熱病に鍼治療を施す場合、浅くすばやく刺して、あたかも沸騰したお湯を手で探るかのように、一触即発の危機のときのように行います。寒冷病に鍼治療を施す場合には、深刺しして鍼を留め、人が別離の情に堪えないといった具合にします。陰分に熱のある病人では、陽明経の足三里を取り、正確に鍼を打って怠らぬようにし、
邪気が下るのを待って鍼を抜きます。邪気が下っていなければ再び刺します。病気が身体上部にあって蔵に属していれば、足の太陰経の合穴である陰陵泉に取ります。病気が身体上部にあって府に属していれば、足の少陽経の合穴である陽陵泉に取ります」。
[本篇の要点]
一、古代に用いられていた鏤鍼・員鍼・提鍼・鋒鍼・鮟鍼・員利鍼・毫鍼・長鍼・大鍼などの九種類の鍼の形状と用途について詳述する。
二、疾・徐・迎・随・開・闔などの刺鍼の手法と補瀉の効果について論述する。
三、十二原穴と蔵府の主治病症の原理について紹介する。
四、疾病というものは治るものであり、「治らないという者は、医術が未熟なのである」と指摘している。
(松木きか訳)
ご覧いただきありがとうございます。 新潟県 長岡市 わかさ 鍼灸 整骨院 はり きゅう koukichi-wakasa.com