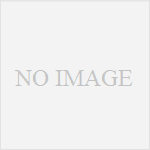脈状解説
六祖脈による大まかな分類
浮に属する脈
浮脈、孔脈、大脈
沈に属する脈
沈脈、伏脈、細脈
沈に属する脈
遅脈、緩脈
数に属する脈
数脈、動脈
虚脈、孔脈、微脈、細脈、軟脈、弱脈
実に属する脈
実脈、緊脈、長脈 力のある脈 弦
各脈状の形状と病理
1、浮脈
形状=軽按でよく感じ、重按して感じなくなる脈。
病理=浮で力があれば陽実。浮で力がなければ陰虚。労倦などによって陰虚熱証。肝虚熱証などの時に現われる。陽虚の浮脈は虚が著しい。
左右の寸囗が浮脈の時は陽実か陽虚である。左右の関上と尺中が浮脈の秋に虚実、遅数に偏らない浮脈が出ていれば健康である。
2、 沈脈
形状=軽按しては感じず、重按してよく感じる脈。
病理=沈で力があれば瘀血(肝実)。これは左関上に現われる。
他の脈診部に沈で力のある脈が現われていれば、その部の臓の熱である。沈で力がない脈ば痰飲などの水毒(湿邪)か陽虚。
冬に虚実、遅数に偏らない沈脈が出ていれば健康である。
3、遅脈
形状=一呼吸問に3拍以下の極めて遅い脈。
病理=遅で力があれば慢性的な冷え。遅で力がなければ腎虚寒証の時に現われやすい。
4、数脈
形状=数脈は一呼吸間に6~7拍動する脈である。
脈の遅数は患者の呼吸と脈拍の関係で診るが、術者が正常な呼吸をしているのであればそれで計ってよい。
病理=数で力のある脈は熱病、肝実熱など内熱、陽経または胃なそ腑に熱がある時など。数で力のない脈は陰虚か陽虚、腫れもの。
5、虚脈
形状=遅、大で軟。重按すると指の下で感じなくなる脈である。
病理=脈経における虚脈の表現に注目して欲しい。これは単に弱いという意味でもないし、祖脈でいう虚脈でもない。非常に限定されたものである。
このような虚脈は、労倦などで津液が虚した時に現われる。本体は
腎虚熱証である。
6、実脈
形状=大きく上下に連なっていて少し強く感じる。これを按圧すると指の下に集まって来て結ぼれた感じになる脈である。
実脈は指を跳ね返すほど強い脈だとは限らない。重按して無くならず、
ますます結ぼれて硬くなれば実脈と取る。
病理=外邪によって熱が発生し、それが陽経や腑に停滞すると実脈になる。
瘀血が停滞しても実脈になる。各熱証や実熱証、陽実証から波及した熱によっても実脈になる。
7、滑脈
形状=滑脈は滑らかで、ころころくりくりしている脈で、数脈に似ている。
往来の形を察して滑と名づけたもので浮沈、遅数、虚実には偏らないが。
病理=疾飲や宿食で内熱、血に熱がある例えば高血圧の人に多く診られる。肺虚肝実証。
8、 濇脈
形状=細く遅い。拍動が滑らかではなく、拍動につまつくような感じが出ている。また散ったような感じの脈である。あるいは時々不整になる。
滑と相対する脈である。これも往来の形を察して濇と名づけられた。
病理=気が虚して停滞している時、あるいは気が虚したために、血が流れなくなって瘀血ができている時などに現われる。
右の寸囗が濇であれば気虚、左の関上が濇であれば肝実のことが多い。
9、弦脈
形状=軽按では感じられず、重按すると弓の弦を張ったように感じる脈である。弦脈は七表の脈に属すといわれているが、これは熱に関係する脈だという意味である。形状からすれば重按して感じる脈である。
病理=六部のどこかに弦で力がない脈があれば、その部の経絡の血が虚して虚熱が発生していると考える。弦で力がある脈であれば、その部の臓腑経絡に熱が停滞していると考える。例肝虚熱証で筋肉痛や神経痛。脾虚肝実熱証。春に虚実、遅数に偏らない弦脈を現わしていれば健康だと考える。
10、緊脈
形状=引き絞った縄に触れたような感じの脈である。緊張している。指にあたる感じが荒い。それで縄に触れたような脈だというのである。
病理=急激な寒冷や痛みや腫れ物などがある時に現われる脈である。
内の病気で緊脈を現わし、なおかつ痛みがあれば要注意である。六部の
どこかに緊脈が現われていれば、その部のの胃気は少ないと考える。
11、孔脈
形状=浮いて大きく軟らかい。重按すると中央が空虚で周囲では感じる脈である。葱の葉を按圧したような感じだといわれている。
病理=浮脈であり虚脈の一種である。中に芯のない脈で全体にも力がない。これは血便、血尿などの出血によって起こる。あるいは他の原因で血がなくなって六部のどこかに現われていれば、その部の血が少なくな
っていると考える。
12、洪脈
形状=軽按して極めて大きく太く感じる脈である。浮脈であり実脈の一種である。夏にあまり強くない洪脈が出ていれば健康である。
後世では、この脈を大ともいう。
病理=陽経に熱が多くなった時に現われる脈である。あるいは病気の勢いが強い時に現われる。もちろん熱証であり実証である。原因は外邪から起こるものと陰虚から起こるものとがある。
13、伏脈
形状=骨が触れるくらい重按して初めて感じられる脈である。
沈に属す脈である。
病理=思慮過度などで極度に気血が虚し九時、慢性的な寒証(湿もある)になっている時、陰経や臓の部に瘀血などのしこり(積聚)がある時などに
現われる。
14、革脈
形状=沈や伏のように重按しないとわからないが、重按した部位で実、大で寸、関、尺の各部よりはみ出した長脈であり、また少し弦のような脈である。
沈で実に属す脈である。しかし、これは本当の実ではなく、津液が虚し
て干からびたために硬くなっているだけである。さらに按圧すると底は
虚している。
病理=津液が不足して内の部に熱が多くなっている時、気諺によって気血が停滞した時などに現われる。腎虚熱証の時に左尺中の脈が革脈を現わしていることがある。
15、微脈
形状=極めて細くまた軟らかい。感じたり感じなかったりする脈である。蜘蛛の糸のようで按圧するとなくなる。
病理=陽虚脈の一種である。極端に気血が虚している時、中焦で気血が生成されない時などに現われる。いずれの場合も寒証として治療する。
16細脈
形状=微脈よりは少し大きくて細い脈である。微脈のように感じたり感じなかったりすることはない。
病理=気血ともに虚して胃の気も少なくなっている時に現われる。
虚脈に属す脈で各寒証の時に現われる。
17、軟脈
形状=浮いて細い脈である。浮で虚に属す脈である。
病理=下焦の陽気が虚して陰陽とも虚した時に現われる。
特に腎虚寒証の時に診ることが多い。
18、弱脈
形状=極めて軟にして沈、細。重按すると無くなりそうになる脈である。沈で虚に属す脈である。
病理=気血ともに虚した時に現われるが、特に血が虚して陽気もなくなった時、肝虚寒証に現われやすい脈である。
19、散脈=・大而散、散者気実血虚、有表無裹
形状=散らばってまとまりのない脈。締まりのない脈である。軽按すると脈の拍動は感じるが、脈管の形まではわからない。もちろん重按すると感じ
ない。
病理=血が虚したために気が衣に集まってきているが、それもなくなろうとしている脈である。この脈が続くようだと予後が悪い。腎虚で三焦の原気
も虚している。
20、緩脈
形状=遅くてゆったりした脈だが遅脈よりは早い。
病理=病的な緩脈は気血ともに虚して循環が悪くなっている時に現われる。あるいは陽気が虚している時に現われる。
健康状態で緩脈が現われれば胃の気が旺盛な脈だとする。
21、促脈
形状=拍動が数で時々止まる脈である。不整脈。
病理=血が不足しているために、早く気が循って血を正常にしようとするために数になる。しかし、血がないので空回りするために時々不整になるのである。この脈は腎虚熱証か肝虚熱証で、心熱や肺熱になっている時に現われやすい。
22、結脈
形状=拍動がゆっくりで時々不整になる脈である。
病理=積などによって陰気が旺盛になり、気血の循環が悪くなった時に現われる。脾虚肝実や肺虚肝実。
23、代脈
形状=拍動が脈のリズムに関係なく止まり、また急に拍動しはじめるような脈である。甚だしい不整脈である。
病理=臓の気血津液が虚し、同時に三焦の原気もなくなろうとしている時に現われる脈である。死脈の一種。
24、動脈
形状=関上の部だけでくりくりと拍動する脈である。
病理=虚労、血便、女子の下血などによって血虚になった時に現われる脈である。腎虚熱証。肝虚熱証
25、牢脈
形状=重按すると堅くて力かおる。拍動は感じるが脈が底に張り付いた感じである。
病理=胃の気なく、肝虚寒証または腎虚寒証で陰陽とも虚。
26、長脈
形状=寸、関、尺の三部はその人なりの長さかおり、普通の脈は寸、関、尺それぞれで感じるものだが、長脈は、たとえば関上からはみ出して寸囗や尺中にまで及んでいるのである。
病理=気血が多く、熱が内に停滞し、三焦が熱して全身に熱感かおる。
脾虚胃実熱で三焦経熱。
27、短脈
形状=長脈の逆で寸、関、尺の縦幅に足りない脈である。たとえば関上の中で小さく拍動して、寸囗や尺中とは独立した感じになっている。
病理=気が虚している時に現われる。同時に気が虚したために血が停滞して陰経に熱が多くなった時にも現われる。ただし、表面の病証は気虚が中心である。食べたものが消化できない時にも現われる。
脾虚または肺虚。
28、大脈
形状二軽按すると浮いて洪、重按すると大で力がないという。つまり洪脈の種ではあるが、重按した時に力がないところに特徴かおる。
病理=血や津液が虚して、いわゆる陰虚になったために、陽に気が多く集まった時に現われる脈である。肝虚熱証。
29、小脈
形状=軽按しても重按しても小さく感じる脈である。
病理=気血とも虚した時に現われる。陽虚。
30、疾脈
形状=数より速い脈である。
病理=熱が多くなっている時に現われる。陽経の熱が主で疾脈なら治るが、臓腑の熱で疾脈であれば治りにくい。陰虚。
ご覧いただきありがとうございます。 新潟県 長岡市 わかさ 鍼灸 整骨院 はり きゅう koukichi-wakasa.com