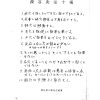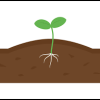08足少陰腎経原文書き下し文現代語訳
腎足少陰之脈、起于小指之下、邪走足心、出于然谷之下、循内踝
之後、別入跟中、以上踹内、出膕内廉、上股内後廉、貫脊、属腎絡
膀胱。其直者、従腎上貫肝膈、入肺中、循喉嚨、挾舌本。其支者、
従肺出絡心、注胸中。
是動則病飢不欲食、面如漆柴、欬唾則有血、喝喝而喘、坐而欲起、目䀮䀮如無所見、心如懸若飢状。気不足則善恐、心惕惕如人将捕之。
是為骨厥。是主腎所生病者、口熱舌乾、咽腫、上気、嗌乾及痛、煩心、心痛、黄疸、腸僻、脊股内後廉痛、痿厥嗜臥、足下熱而痛。
為此諸病、盛則写之、虚則補之、熱則疾之、寒則留之、陥下則灸之、
不盛不虚、以経取之。灸則強食生肉、緩帯披髪、大杖重履而歩。盛
者寸口大再倍千人迎、虚者寸口反小干人迎也。
腎 足の少陰の脈は、小指の下に起こり、邪めに足心に走り、然谷の下に出で、内踝の後を循り、別れて跟中に入り、以て踹内を上り、膕の内廉に出で、股内の後廉を上り、脊を貫き、腎に属して膀胱を絡う。其の直なる者は、腎より上りて肝・膈を貫き、肺中に入り、喉嚨を循り、舌本を挾む。其の支なる者は、肺より出でて心を絡い、胸中に注ぐ。
是れ動けば則ち飢ゆるも食を欲せず、面は漆柴の如く、欬唾すれば則ち血あり、喝喝として喘ぎ、坐して起たんと欲すれば、目は䀮䀮として見る所なきが如く、心は懸くるが如く飢ゆるの状の若きを病む。気足らざれば則ち善く恐れ、心惕惕として人の将にこれを捕え
んとするが如し。是れ骨厥と為す。是れ腎の生ずる所の
病を主る者、口熱して舌乾き、咽腫れ、上気し、嗌乾き及び痛み、煩心し、心痛し、黄疸し、腸澼し、脊股の内後廉痛み、痿厥して臥するを嗜み、足下熱して痛む。
此の諸病を為むるに、盛んなるは則ちこれを写し、虚するは則ちこれを補い、熱するは則ちこれを疾くし、寒ゆるは則ちこれを留め、陥下するは則ちこれに灸し、
盛んならず虚ならざるは、経を以てこれを取る。
灸すれば則ち強いて生肉を食らわしめ、帯を緩め髪を披き、大杖もて重き履にて歩ましむ。
盛んなる者は寸口の大なること人迎に再倍し、虚する者は寸口反って人迎より小なるなり。
【注釈】
邪め-ここでは「斜」字と同じ。面は漆柴の如し-「漆」は黒色。「柴」は木柴。「漆柴」とはかび腐れした黒色の木材である。「面は漆柴の如し」とは、病人の顔色が黒くて光沢がなくなっていることを形容している。
䀮䀮-「䀮䀮」とは物を視てもはっきりしないこと。『玉篇』目部に「䀮とは目が明らかでないこと」とある。
【現代語訳】
「足の少陰腎経は、足の小趾の下から起こり、斜めに足心に走り、内踝の前の大骨にある然谷穴の下に出て、内踝骨の後に循り転じて眼中に入り、ここから上行してふくらはぎの内側を経て、膕窩の内側に出る。再び大
腿の内側の後縁に循り、脊柱を貫き、腎蔵に連属し、本蔵と表裏の膀胱と連絡する。直行している経脈は、腎より上行して肝に至り、横隔膜を通過して、肺に入り、喉に循り舌根を挾む。其の支脈は、肺より出て心に連絡し、胸中に注いで、手の厥陰経と相い接する。
外邪が本経を侵犯して生ずる病証は、飢えているのに食欲がなく、顔色が黒くて光沢がなく、欬唾すると血が混じり、ぜいぜいとした呼吸となり、坐っていて急に立とうとすると、目に見えるものが曖昧模糊としてはっきりしなくなり、心に気懸りがあって飢えているように見える。気が不足すると恐懼し、心中びくびくして人が彼を捕捉しようとしているかのようになる。これを骨厥という。本経脈が主っている腎蔵によって生ずる病変は、口が熱し、舌が乾き、咽部が腫れ、気が上逆して喉が乾いて痛む。心中が煩悶して痛み、黄疸し、下痢し、脊背や大腿の内側の後縁が痛み、足が痿えて厥冷し、よく睡りたがり、足心が熱して痛む。
このような病証には、実証には瀉法を用い、虚証には補法を用い、熱証には速刺法を用い、寒証には置鍼法を用い、脈が虚陥していれば灸法を用い、実でもなく虚でもなければ本経に従って治療する。
灸法を用いた後は、強いて栄養のあるものを食べさせて体の回復を促し、腰帯を緩め、髪の毛を解かせ、手はがっちりした杖で支え、
足には重い靴を履かせて散歩させ、こうして気血を暢びのびと通じさせるのである。
本経の気が盛んとは、寸口脈が人迎脈と比較して二倍大きいことである。気が虚しているとは、寸口脈がかえって人迎脈より小さいことである。
【訳注】
(一)三倍になる。
黄帝内経霊枢: 現代語訳 (上巻)より引用
ご覧いただきありがとうございます。 新潟県 長岡市 わかさ 鍼灸 整骨院 はり きゅう koukichi-wakasa.com